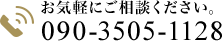2025/09/25
『低温排熱から冷却水を生成する設備を飲料工場に導入・活用する場合の設計事例』
“Design example of introducing and utilizing equipment to generate cooling water from low-temperature waste heat in a beverage factory”
1. はじめに
低温排熱(50~80℃程度)を活用して冷却水を生成する設備は、エネルギーの有効利用やカーボンニュートラルの推進に貢献する重要な技術である。以下に代表的な方式とその特徴、飲料工場に導入・活用した設計事例を紹介する。
2. 低温排熱から冷却水を生成する設備
(1) 主な設備方式と仕組み
1 吸収式冷凍機(Absorption Chiller)
・原理:低温の排熱(温水や蒸気)を熱源として、冷媒(通常は水)を使って冷却水を生成。
・特徴:1) 電力消費が少ない(電動コンプレッサー不要)
2) フロンなどの環境負荷の高い冷媒を使わず、水を冷媒に使用
3) 廃熱の温度が高いほど効率が良い
・用途:空調、プロセス冷却、地域冷暖房など
2 ヒートポンプ式冷却設備備
・原理:低温排熱を熱交換器で回収し、ヒートポンプで温度を調整して冷却水や温水を生成。
・特徴:1) 廃水や循環冷却水の熱を再利用
2) 高効率(COPが高く、消費電力に対して多くの熱を回収)
3) 工場の水使用量や燃料使用量の削減に貢献
・製品例(参考):三浦工業株式会社「未利用熱活用ヒートポンプVH」
https://www.miuraz.co.jp/product/thermoelectric/vh.html
3 多段ヒートポンプ+蓄熱槽方式
・原理:40℃程度の排熱を段階的に昇温し、最終的に120℃の水蒸気を生成して冷却や水素製造などに活用。
・特徴:1) 低温排熱でも高温蒸気を生成可能
2) 蓄熱槽を介して安定した運転が可能
3) 高効率(COP 2.0以上)
(2) メリットと導入効果
1 省エネ:未利用熱を活用することで電力や燃料の使用量を削減
2 環境負荷低減:CO₂排出量の削減、フロン不使用など
3 コスト削減:冷却水や温水の生成にかかるランニングコストを抑制
4 設備の長寿命化:冷却効率の向上により機器の負荷軽減
3. 低温排熱を活用して冷却水を生成する設備の導入コスト
低温排熱を活用して冷却水を生成する設備の導入コストは、設備の種類・規模・既存インフラとの接続状況によって大きく異なります。以下に代表的な方式ごとのコスト感とポイントについて述べる。
(1) 導入コストの目安と要因
実際の見積もりは現場調査や仕様設計によって変動するが、導入コストの目安を表1.に示す。
表1. 設備方式と初期導入費用の目安
| 設備方式 | 初期導入費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 吸収式冷凍機 | 約1,000万~5,000万円 | 排熱温度が高いほど効率的。 大型設備向け |
| ヒートポンプ式冷却設備 | 約500万~3,000万円 | 小~中規模工場向け。 既存設備との連携でコスト変動 |
| 多段ヒートポンプ +蓄熱槽方式 |
約3,000万~1億円以上 | 高温蒸気生成など特殊用途向け |
(2) コストに影響する主な要因
1 排熱の温度と量:低温すぎると回収効率が下がり、設備が大型化しやすい
2 冷却水の必要量:用途(空調、プロセス冷却など)に応じて設備容量が変わる
3 既存設備との接続性:既存の配管や熱源との互換性が高ければコスト削減可能
4 補助金・助成制度の活用:環境省や経産省の省エネ補助金対象になる場合あり
(3) ランニングコストと回収期間
1 ヒートポンプ式では電力消費が少なく、年間数百万円の燃料費削減が可能なケースもある
2 一般的に5~10年程度で投資回収できるとされているが、補助金活用で短縮可能
(4) 補助金・支援制度の例
補助金・支援制度を活用する場合は、年度ごとに内容が変わるため、最新情報の確認が必須である。
1 省エネルギー設備導入補助金(経産省)
2 地域脱炭素促進事業(環境省)
3 中小企業向けエネルギー効率化支援
4. 冷却水の必要量の算定
冷却水の必要量は、冷却対象の熱量や温度差をもとに計算できる。目的に応じていくつかの方法があるが、ここでは代表的な2つの計算方法を示す。
(1) 方法:混合による冷却(比率で計算)
例えば、80〔℃〕の水1000〔kg〕を40〔℃〕に冷却するために、20〔℃〕の冷却水を使う場合:
【計算式】
(80〔℃〕×1000〔kg〕+20〔℃〕×X〔kg〕)/(1000〔kg〕+X〔kg〕)=40〔℃〕
X=2000〔kg〕となり、冷却水は2000〔kg〕必要になる。
1 高温水と目標温度の差:80〔℃〕− 40〔℃〕= 40〔℃〕
2 冷却水と目標温度の差:40〔℃〕− 20〔℃〕= 20〔℃〕
3 比率:40 : 20 = 2 : 1 → 冷却水は高温水の2倍
(2) 方法:熱量ベースで計算(冷却能力の算出)
冷却対象の熱量から必要な冷却水量を求める方法
【基本式】
Q=m×C×ΔT
Q:必要な冷却熱量〔kcal〕
m:冷却水の質量〔kg〕
C:比熱〔水の場合は1kcal/kg℃〕
ΔT:冷却水の温度上昇〔℃〕
この式を変形して、必要な冷却水量を求める。
例:
冷却対象から100,000 kcalの熱を除去したい。冷却水の入口温度が20℃、出口温度が30℃(ΔT = 10℃)の場合:
m=Q /(C×ΔT)=100,000〔kcal〕/(1〔kcal/kg℃〕×10〔℃〕)=10,000〔kg〕
10トンの冷却水が必要となる。
(3) 留意点
1 冷却水の入口・出口温度差(ΔT)が小さいと、必要量は増える
2 連続運転かバッチ処理かで計算方法が異なる
3 安全率(20~30%)を加味するのが一般的である
必要量の計算は、冷却対象の種類(液体・装置・空気など)によっても変わるので注意する。
5. 飲料工場での冷却水使用の典型的なケースでの事例
必要な冷却水量について具体的な計算例で示す。
(1) ケース設定:工場の熱交換器の冷却
▶ 条件:
・冷却対象:加熱されたプロセス水(例:反応槽から出た水)
・水量:2,000〔 kg(2トン)〕
・初期温度:80〔℃〕
・目標温度:40〔℃〕
・使用する冷却水の温度:20〔℃〕
・冷却水の出口温度:30〔℃(ΔT = 10℃)〕
▶ 計算:
ステップ①:除去すべき熱量の計算
Q=m×C×ΔT=2,000〔kg〕×1〔kcal/kg℃〕×(80〔℃〕-40〔℃〕)=80,000〔kcal〕
ステップ②:必要な冷却水量の計算
冷却水が吸収できる熱量
Q=m×C×ΔT=1〔kg〕×1〔kcal/kg℃〕×(30〔℃〕-20〔℃〕)=10〔kcal/kg〕
m=Q /(C×ΔT)=80,000〔kcal〕/(1〔kcal/kg℃〕×10〔℃〕)=8,000〔kg〕
▶ 結果:
このケースでは、2トンの高温水を40〔℃〕まで冷却するために、20〔℃〕の冷却水が約8トン必要になる。
▶ 補足:
1 冷却水の出口温度をもっと高く設定できれば(例:35〔℃〕)、必要量は減る
2 実際の設計では、安全率(10~30〔%〕)を加味して、冷却水量は余裕を持って確保する
3 循環式冷却塔を使う場合は、冷却水の再利用も可能である
(2) ケース設定:冷却対象が少量で温度差が大きい場合
▶ 条件:
・高温水:500〔kg〕
・初期温度:90〔℃〕
・目標温度:40〔℃〕
・冷却水:入口20〔℃〕 → 出口30〔℃〕(ΔT = 10〔℃〕)
▶ 計算:
ステップ①:除去すべき熱量の計算
Q=500〔kg〕×1〔kcal/kg℃〕×(90〔℃〕- 40〔℃〕)=25,000〔kcal〕
ステップ②:冷却水が吸収できる熱量(1〔kg〕あたり)の計算
1×10〔℃〕=10〔kcal〕
ステップ③:必要な冷却水量の計算
m=25,000/10=2,500〔kg〕(2.5トン)
(3) ケース設定:冷却水の出口温度を高く設定する場合(効率重視)
▶ 条件:
・高温水:1,000〔kg〕
・初期温度:70〔℃〕
・目標温度:40〔℃〕
・冷却水:入口20〔℃〕→ 出口40〔℃〕(ΔT = 20〔℃〕)
▶ 計算:
ステップ①:除去すべき熱量の計算
Q=1,000〔kg〕×1〔kcal/kg℃〕×(70〔℃〕- 40〔℃〕)=30,000〔kcal〕
ステップ②:冷却水が吸収できる熱量(1〔kg〕あたり)の計算
1×20〔℃〕=20〔kcal〕
ステップ③:必要な冷却水量の計算
m=35,000/20=1,500〔kg〕(1.5トン)
このように、冷却水の出口温度を高く設定することで必要量を減らすことができる。但し、出口温度が高すぎると冷却効率が下がるので、設備設計とのバランスが重要になる。
6. 飲料の無菌充填設備用途での計算例
無菌充填設備では、飲料(例:ミネラルウォーター、清涼飲料など)を殺菌後に冷却してから充填するため、冷却水の必要量の計算は非常に重要である。以下に、実際のプロセスを想定した具体的な計算例を示す。
(1) 無菌充填設備における冷却水量の計算例
▶ 想定条件:
・飲料の処理量:6,000 L/h(= 6,000 kg/h)
・飲料の殺菌温度:85℃(プレート式殺菌機使用)
・充填温度:30℃(無菌充填の一般的温度)
・冷却水の入口温度:20℃
・冷却水の出口温度:35℃(ΔT = 15℃)
・比熱:水の比熱 = 1 kcal/kg℃
▶ 計算:
ステップ①:除去すべき熱量の計算
飲料を85〔℃〕→ 30〔℃〕に冷却するための熱量:
Q=6,000〔kg〕×1〔kcal/kg℃〕×(85〔℃〕- 30〔℃〕)=330,000〔kcal〕
ステップ②:水が吸収できる熱量(1〔kg〕あたり)の計算
冷却水1〔kg〕が吸収できる熱量
1×(35〔℃〕- 20〔℃〕)=15〔kcal/kg〕
ステップ③:必要な冷却水量の計算
m=300,000〔kcal〕/15〔kcal/kg〕=22,000〔kg/h〕(=22〔m3/h〕)
▶ 結果:
この条件では、毎時6,000〔L〕の飲料を無菌充填温度まで冷却するには、約22トン(22,000〔L〕)の冷却水が必要になる。
▶ 補足:
1 プレート式熱交換器を使用すると、伝熱効率が高く冷却水量を抑えられる傾向がある
2 冷却水の出口温度をさらに上げる(例:40〔℃〕)ことで、必要量を減らすことも可能である
3 無菌充填では、冷却後の飲料を無菌環境下で充填するため、冷却水の衛生管理(ろ過・殺菌)も重要である
(2) PETボトルのサイズは1〔L〕~2〔L〕やライン速度1〔m/s〕、冷却方式(間接冷却)での設計計算例
PETボトル(1〔L〕~2〔L〕)を無菌充填ラインで間接冷却するケースを想定し、冷却水の必要量を設計計算例で示す。
▶ 設計条件(想定):
・ボトルサイズ:1〔L〕~2〔L〕(平均1.5〔L〕で計算)
・ライン速度:1〔m/s〕(搬送ライン上のボトル移動速度)
・ボトル間隔:約0.2 〔m〕(密な搬送)
・冷却方式:間接冷却(プレート式熱交換器)
・飲料温度:殺菌後85〔℃〕 → 充填温度30〔℃〕
・冷却水温度:入口20〔℃〕 → 出口35〔℃〕(ΔT = 15〔℃〕)
・比熱:水の比熱 = 1〔kcal/kg℃〕
▶ 計算:
ステップ①:処理本数の算出
ライン速度1〔m/s〕、ボトル間隔0.2〔m〕→毎秒5本処理→毎時:
5〔本/秒〕× 3600〔秒〕=18,000〔本/h〕
ステップ②:飲料処理量の算出
平均ボトル容量1.5〔L〕
18,000〔本〕× 1.5〔L〕=27,000〔L/h〕(=27,000〔kg/h〕)
ステップ③:除去すべき熱量の計算
Q=27,000〔kg〕×1×(85〔℃〕- 30〔℃〕)=1,485,000〔kcal/h〕
ステップ④:冷却水が吸収できる熱量(1〔kg〕あたり)の計算
1×(35〔℃〕- 20〔℃〕)=15〔kcal/kg〕
ステップ⑤:必要な冷却水量の計算
m=1,485,000〔kcal〕/15〔kcal/kg〕=99,000〔kg/h〕(=99〔m3/h〕)
▶ 結果:
この条件では、毎時約99トンの冷却水が必要になる。これはかなりの量なので、冷却水の循環再利用(冷却塔)や蓄熱槽の併用が重要になる。
▶ 設計上の注意点:
1 プレート式熱交換器の伝熱面積と流速を最適化することで冷却効率を向上させることができる
2 冷却水の出口温度をさらに上げる(例:40℃)と必要量は減るが、冷却効率に注意が必要である
3 無菌充填では冷却水の衛生管理(ろ過・UV殺菌など)も重要な要素になる
(3) ラインの実際の構成(並列ライン数:2ライン、ボトル形状:ゲーブルトップ(紙容器)、冷却時間:1〔h〕)における設計計算例
ゲーブルトップ紙容器を使用した無菌充填ライン(2ライン構成)での冷却水必要量の設計計算例を示す。
▶ 設計条件(想定):
・容器形状:ゲーブルトップ紙容器(1〔L〕)
・並列ライン数:2ライン
・ライン速度:1 〔m/s〕(搬送速度)
・容器間隔:約0.2 〔m〕(密な搬送)
・冷却時間:1時間(連続運転)
・飲料温度:殺菌後85〔℃〕 → 充填温度30〔℃〕
・冷却水温度:入口20〔℃〕 → 出口35〔℃〕(ΔT = 15〔℃〕)
・比熱:水の比熱 = 1〔kcal/kg℃〕
▶ 計算:
ステップ①:処理本数の算出
搬送速度1〔m/s〕、容器間隔0.2〔m〕→毎秒5本処理→並列2ライン→毎秒10本:
10〔本/秒〕× 3600〔秒〕=36,000〔本/h〕
ステップ②:飲料処理量の算出
容器容量1〔L〕(=1〔kg〕)
飲料処理量
36,000〔本〕× 1〔kg〕=36,000〔kg/h〕
ステップ③:除去すべき熱量の計算
温度差:殺菌後85〔℃〕 → 充填温度30〔℃〕
Q=36,000〔kg〕×1×(85〔℃〕- 30〔℃〕)=1,980,000〔kcal/h〕
ステップ④:冷却水が吸収できる熱量(1〔kg〕あたり)の計算
1×(35〔℃〕- 20〔℃〕)=15〔kcal/kg〕
ステップ⑤:必要な冷却水量の計算
m=1,980,000〔kcal〕/15〔kcal/kg〕=132,000〔kg/h〕(=132〔m3/h〕)
▶ 結果:
この条件では、毎時約132トンの冷却水が必要になる。
▶ 実務上の対策と提案:
1 冷却塔やチラーによる循環冷却を導入し、冷却水の再利用を図る
2 高熱槽+ヒートポンプを併用することで、ピーク時の負荷を分散する
3 プレート式熱交換器を使用して、伝熱効率を最大化する
4 冷却水出口温度を40℃に設定すれば、必要量は約110トン/hに減少できる
7.最後に
設計計算はあくまで理論値なので、実際の設備設計では安全率(10~30%)を加味し、冷却水の供給能力や衛生管理(フィルター、UV殺菌など)も考慮する必要がる。また設備投資の最適化と省エネ・環境対策の両立させることも検討する。
以上