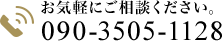2025/10/20
『食品機械・機器(充填・包装装置)の基礎知識』
“Food Machinery and
Equipment (Filling and Packaging Equipment) Basic Knowledge”
【Ⅰ】. はじめに
食品製造工程別にラインを構成する「食品充填・包装」に関連する代表的な食品機械・機器(充填・包装装置)について製品別に解説する。
1. 充填包装機
充填包装機とは、容器に対して内容物を詰める、充填する装置。内容物は液体や粉末、固形食品そのものなど多岐に渡る。充填する製品によって物性が様々に異なるので、それぞれに合った充填機が存在します。物性以外にも充填物のサイズや形状、充填能力などで充填方法も異ってくる。また、内容物の充填量は一定である必要がある場合が多いので、定量性、安定性が求められる装置である。充填機は食品以外でも医薬品、化粧品など、生活に密着したあらゆる場面で利用されている。充填包装機は、内容物の性状や容器の形状に応じて、チューブポンプ式、ロータリー式、スクリュー式、振動フィーダー式、ピストン式のタイプに分類される。飲料分野では、無菌充填システム、ホットパック充填などがある。
2. 横ピロー包装装置
ピロー包装とは、製品が包装された形が枕(ピロー)に似ていることからその名称が付いている。特徴は、製品をベルトコンベヤで横方向に搬送しながら包装し、固形物やトレー入り製品に適している。フィルムが製品の上下を包み、背面でシール方式である。適した製品例は、食パン、菓子パン、おにぎり、インスタントラーメン(単品)、トレー入り冷凍食品(餃子、シューマイなど)ソーセージ、ハム、クッキー、海苔などである。利点は、製品の形状が安定している場合に高速包装が可能で、トレーとの組み合わせで保護性が高い。最も普及している包装スタイルの一つです。ピロー包装機の種類は大きく分けて横型ピロー包装機と縦型ピロー包装機がある。製品の性質や包装形態、ライン構成によって選定が変わってくる。
3. 縦ピロー包装装置
横ピロー包装装置と縦ピロー包装装置は、どちらも「ピロー包装」と呼ばれる枕状の形に仕上げる包装方式ですが、構造や適した製品が異なる。縦ピロー包装装置の特徴は、フィルムを筒状に成形し、製品を上から落下させて充填する。背面・底面・上部を順にシールして密封し、液体や粉体、バラ物に適している。適した製品例は、スープ、調味料、小麦粉、コーヒー、スナック菓子、カット野菜、ゼリー、キャンディ、ペットフードなどになる。利点は、液体や粉体など、流動性のある製品に強い。自動計量やフィルムスプライサーなどの機能で効率化可能である。注意点として製品が落下するため、衝撃に弱いものには不向きで、包装中に割れや欠けが起きる可能性があるため、事前検証が重要になる。
4. 深絞り包装装置
深絞り包装機とは、プラスチックのシート(ボトム)を包装対象に合せて熱で成形し、そこに内容物を投入した後、上部からシート(トップ)を溶着する事によって包装する装置。基本構造と工程は、ボトムフィルムの成形:加熱されたプラスチックシート(ボトム材)を金型で成形し、食品を入れるポケットを作り、成形されたポケットに食品を投入。手作業または自動で充填を行う。その後、を上からトップフィルムをかぶせ、熱シールで密閉。真空やガス置換を行い、トップフィルムを溶着する。メリットは、真空状態で包装することで酸化や好気性菌の繁殖を抑制し、賞味期限を延長でき、成形されたトレーにより、商品が安定して見栄え良く陳列可能。包装面積が広く、デザインや情報表示に適していると共に包装された製品を縦横にカットし、個包装に仕上げることができる。用途例は、ハム、ソーセージ、サラダチキン、ゆで卵などの加工食品および医療器具や薬品など衛生管理が重要な製品にも活用されている。
5. 真空包装機
食品工場で使用される真空包装機は、食品を密封した状態で空気を抜き、真空状態にする装置。その主な働きは、酸素の除去、微生物の抑制、湿気の防止、食品の品質保持、外部汚染の防止、包装の効率化などがある。まず、真空包装機は袋や容器内の空気を排気して酸素を取り除く。これにより、食品中の酸素がなくなり、酸化反応が抑制されます。また、真空状態にすることで微生物の成長が抑制され、食品の腐敗が遅延される。さらに、真空包装機は湿気の侵入を防ぎ、食品を密封することで湿気が遮断され、食品の乾燥や質の低下が防がれる。これにより、食品の風味、色、質感などが保たれる。同時に、真空包装機により外部からの微生物や汚染物質の侵入が防がれる。これにより、食品の安全性が向上し、衛生的な状態で保管・流通される。また、真空包装機は自動化されたプロセスにより包装作業を効率化する。これにより、生産性が向上し、コストや労力が削減され、真空包装機は食品の品質管理や安全性確保に不可欠な役割を果たしている。食品の鮮度や保存期間を延長し、消費者に安全で高品質な製品を提供するために欠かせない装置である。
6. シュリンク包装装置
シュリンク包装機とは、熱によって収縮する透明なフィルムで商品をパッケージする装置。肉や野菜、パンやカップ麺などの食品、飲料、化粧品、日用品、医薬品、書籍など、様々な業界や分野で広く採用されているが、各種仕様の選定を誤ると商品に悪影響を及ぼすリスクがあるため、注意が必要である。シュリンク包装機は、フィルムを商品にかけた後、熱風などでフィルムを熱収縮させて包装する。そのため、チョコレートや高温に弱い商品を扱う際には、事前に使用可能か確認する必要がある。また、シュリンク包装機には、幅広い種類や機能があり、適切な選定が商品の品質を保ち、梱包の効果を最大限に引き出すために重要である。
7. 給袋包装装置
給袋包装機とは、あらかじめ成形されたパウチを包装機の袋供給レール部分に供給し、包装機内で製品の充填密封シールを行うだけでなく、賞味期限や製造番号の印字捺印、印字検査まで可能な設備。お菓子で採用されているチャックシール(ジッパー)付きのパウチや、冷凍可能な飲料、詰め替え用シャンプーで良くみられるスパウト付きのパウチなど幅広く採用されている。対象製品もドライ製品だけでなく、ウェット用、スパウト袋用と多様な包材、製品に対応可能な設備である。
8. クラフトシーラ
クラフトシーラとは、重袋(重いものを包装する袋)の開口部を閉じる装置。重袋には、クラフト紙を素材としたクラフト重袋とポリエチレンフィルムを素材としたポリ重袋の2種類が主流であるが、袋の材質によってシール方式が変わってくる。1袋20~30㎏程度の粉体原料や包装工程で良く使用するホットメルトのチップ糊を梱包する包材としてクラフト重袋が良く使用される。袋状態でパレット積みされて搬送、納品されることが多く、パレットに積載した状態で破袋(開け口などが開口しない)しない強度が必要になる。強度を出すために開口部を縫合する、開口部を折り込んでシールするといった方法でシールされている。
9. ホットメルト装置
食品工場で使用されるホットメルト装置は、包装材料(例プラスチックフィルムや紙など)の接着に使用される。包装材料を接着するための接着剤(ホットメルト接着剤)を溶かし、必要な場所に正確に塗布することで、包装材料を密閉し、製品を保護する。また、包装袋や容器のシールを形成するためにも使用される。例えば、フィルム包装された食品の端部や開口部を密封するために、ホットメルト接着剤を使用してシールを形成し、更に製品にラベルを貼り付ける際にもラベルを製品に固定するために、ホットメルト接着剤が使用され、製品に適切に貼り付けられる。そして、食品や食品包装の表面に保護フィルムを貼り付ける際にも使用されている。ホットメルト装置は、高速生産ラインにおいても使用されることがあります。高速の包装ラインにおいても、ホットメルト接着剤は迅速かつ効果的に使用され、生産性を向上させている。
10. パーツフィーダ
パーツフィーダとは部品供給装置とも呼ばれ、ワーク(原料、加工物)を整列させて次工程に供給する装置。貯蔵、整列、供給の3つの機能を持ち、特に整列工程では部品や用途によって最適な整列を行う必要がある。食品の製造では主に、加工や包装のラインで利用され、PETボトルやボトルキャップなどの供給装置として用いられている。ワークの性質、整列の向き、供給方法は多岐にわたるため、多くは受注生産によって専用装置としてラインに組み込まれている。
11. 製函・箱組立装置
製函機とは、シート状態の段ボールを1枚ずつ取り出し、箱形状の成形し段ボール箱を作る(製函作業)を行装置。段ボールの上面、下面それぞれにフラップ(折り曲げてフタをする内蓋、外蓋)があり、フラップの折り込み、接着する。接着方法として粘着テープ、クラフトテープ、ホットメルト、ステープルなどがあり、段ボールを事前に組み立てておく必要がないことで省スペース化の実現や、高能力による生産性の向上など比較的課題解決しやすい工程である
12. 封函装置
封函機とは、製品を箱詰めした後の段ボール上下面にテープを貼り、箱に封をする装置。封函方法としてテープでの封函以外にホットメルトと呼ばれる糊で封函する方法もある。また、水湿性ガムテープを使用し切手、収入印紙などのように水で湿らすことで貼る(粘着させる)ことが出来るテープで封函する装置もある。保管が低温(マイナス)から高温の環境でも剥離しない、わざと開封痕が残すようなメリットもありる。上下貼りや封函用テープの貼り方、箱の対応サイズ、前後工程との連結など様々な仕様がある。封函処理箱の数、サイズの種類、ケースも段ボールだけでなく、発泡スチロールに対応しているものもあり、現場の温湿度などの作業環境や封函する内容物などによっても最適な仕様は変わってくる。
13. 自動箱詰装置
自動箱詰め機とは、製函、成形されたダンボールに包装された製品を装填する装置。別名、オートケーサやケースパッカと呼ばれる。製品を出荷する形態として段ボールに詰めて出荷される場合が多いが、食品工場、包装固定の中でも自動化、省人化が進んでいる工程の一つになる。ロボットを用いて箱詰めを行う方法もあり、箱詰め工程を自動化することにより、1ケース入れ忘れや入れ方向の間違いなど人的ミスの軽減、省人化に対策として活用されている。
14. 製品自動投入・供給装置
製品自動投入・供給装置とは、包装工程における製品の自動投入、包材の自動供給や、加工工程における原料の自動供給を行う搬送装置。その性質から特定の対象物をハンドリングする機器のほかに、各工場で専用の機器としてオーダーメイドの場合や、製造機器の一部に組み込まれていたりすることもある。本来人手で行う単純作業を自動化する装置であり、生産効率の向上、工場の自動化には欠かせない装置である。
15. シーラ
シーラとは、その名の通り、フィルムをシールする装置であり、商品を密封するために使用される。「シールする」とは、フィルム包材を熱溶着や溶断などの方法で封をすることを指す。シーラは、パック、紙、箱、ポリエチレンやクラフト素材などの包装工程において欠かせない装置であり、形状や機能、用途、内容物、食品に応じてさまざまなタイプがあります。例えば、工場で使用される大型のシーラから、卓上で使える小型のシーラまで幅広く存在し、最適なものを選ぶことが重要である。選び方としては、商品の種類や包装資材(テープやポリ袋、バッグなど)、表示の幅、シーラの性能や調整のしやすさ、対応できる包材の厚みなど、さまざまな要素に基づく判断が必要となる。シーラは、給袋包装機やピロー包装機など、他の包装機にもシール部として組み込まれるが、それに適した機種を選ぶことが求められる。
16. カートニングマシン
カートニングマシンとは、カートンと呼ばれる厚紙や段ボールなどでつくられた紙材の箱を製函、その後カートンへの製品投入、封函を一台で行う装置。別名カートナーと呼ばれる。製菓、レトルト食品などの小箱サイズのものから大型のものまで食品製造現場では非常に幅広く採用されている食品製造装置の一つ。装置の能力も1分間当たり数十個~300個程度包装できるスペックで幅広く製品がある。
17. カードディスペンサ
カードディスペンサとは、製品に同封、もしくは付属するカードの払い出し、及び貼り付けを行う装置。カード以外でも、厚紙を利用した台紙のようなものを供給する際にも利用されます。性質上、包装ラインの付属機器として利用される事が多い装置である。人手作業によるカードの貼付けやボール紙を行う場合は、作業従事者による供給のバラツキや作業習熟度合いによって作業スピードが追い付かないなどの懸念があるが、自動化することにより人の作業由来で発生する供給精度や供給能力バラツキに左右されないメリットもある。
18. 組み合わせ自動計量装置
自動秤量機とは、次工程で包装する個包装1個分の製品量を計量する装置。計量したい製品や、計量能力(タクトタイム)によって様々な仕様がある。自動秤量機は別名自動計量機、組み合わせ計量機、コンピュータスケールと装置メーカーや仕様により異なることがあるため、検索する際の参考として覚えておいてください。食品工場では粉体原料の1バッチ分の計量や、包装機前工程の1個分の計量といった幅広い工程で採用されている。
19. パーツカウンタ
パーツカウンタとは、部品の計数作業を自動化する装置。別名「計数器」とも呼ばれる。計数対象の大きさ、数、回数によっては、人による作業には限界があるので、専用の機器を使用して計数を行う。食品の場合、内容量は重量を基準に決められている製品と、個数を基準に決められている製品があるので、個数を基準に内容量が決まっている製品にはパーツカウンタを用いて規定個数をカウントしながら、包装工程に送っていくなどの用途となる。
20. 自動計量装置
自動計量器とは、粉体原料やチップ状の原料を自動で計量する装置。食品製造現場では原料の投入作業は特に作業負荷の高い工程であり、計量ミスなどによる配合ミスといった重大トラブルにも繋がる工程である。重量物の運搬や原料の投入作業での作業環境の悪さなど課題の多い工程であるため、自動計量器も幅広く採用されている。自動計量器によって計量作業が自動化されることにより、作業負荷の軽減、計量間違いのリスクも大幅に軽減されている。
21. バンド装置
バンド装置とは、製品にPPバンドを巻き付けて梱包する装置。PPとはポリプロピレンの事で、多くは段ボール箱の梱包、荷締めに利用されている。食品製造現場では出荷製品を2個で1括りとして出荷する形態もある。出荷製品をパレット積みする場合に2個1括りにする方が安定するという意図で使用し、段ボールが開梱されていないことを証明する用途としてバンドを掛ける場合もある。パレット積み担当者が段ボールを運搬する際にバンドを持ち手として使用する用途など様々な用途がある。
22. ストレッチフィルム包装装置
ストレッチフィルム包装機とは、パレットに積まれた製品にストレッチフィルムを巻き付ける装置。食品工場製造現場では、物流工程や出荷前完成品の保管倉庫で多く採用されている。輸送、荷役、保管時の荷崩れを防止し、少しの傷、汚れや水濡れからも守ります。1日に数百枚ものパレット積み製品にストレッチフィルムを巻き付ける作業は作業性も悪く、作業従事者の身体的負担も非常に大きくなることから、最近では、バンド装置の代わりに個包装ストレッチフィルム包装機も上市されている。段ボールにノベルティを貼り付ける際などでもストレッチフィルム包装機は活用されている。生産性向上、省人化に繋がり職場環境改善にも繋がる装置となる。
23. ラベル貼り装置
ラベル貼り機(ラベラー)とは、商品名、製造年月日、賞味期限、バーコードなど、様々なラベル貼りを行う装置。ラベル貼り工程は主に、印字、剥離、貼り付けの3つの工程があり、それぞれの工程いずれかのみを行う装置と、2種類以上、もしくは全ての工程を担う機器に分類される。また貼り付ける対象の形状、材質によっても専用の装置がある。ラベラーを使用する事によって作業効率の向上だけでなく、貼り付けミスやズレ、ゆがみを防ぎ、均一な商品づくりが可能になる。
24. 包材・資材
包材・資材とは、食品を入れる容器やトレー、フィルムやパウチといった内容物を保護し、運搬しやすくするものの総称である。内容物(製造する製品)によって使用する資材は異なる。包材・資材は単に食品を包んで運ぶためだけの用途ではなく、外部からの衝撃や湿度、光、酸素などの影響を遮断し、品質保持のために必要不可欠なものである。また、消費者に対し賞味期限や原材料といった必要な情報を届ける用途として重要な役割を果たしている。さらに消費者の購入意欲を向上させるために、パッケージデザインや保存性を向上させるジッパー付きの包材など、より付加価値を高める要素としての機能も兼ねている。
【Ⅱ】. 最後に
次回は『食品機械・機器(検査・検品)の基礎知識』として食品製造工程別にラインを構成する代表的な食品機械・機器(装置)について製品別に解説する。
以上
【参考文献】
「食品設備・機器事典」編集:食品設備・機器事典編集委員会 発行:産業調査会