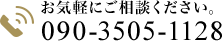2025/09/25
技術用語解説77『脱アルコール製法 (De-alcoholization process)』
1. アルコール飲料の脱アルコール製法とは
脱アルコール製法は、通常のアルコール飲料からアルコール分を取り除いてノンアルコール飲料を作る技術で、特にノンアルコールビールの製造に使われている。以下に詳しく解説する。
1-1.脱アルコール製法の主な種類
- (1) 加熱除去法(蒸留法)
– アルコールの沸点(約78.5℃)を利用して、加熱により蒸発させる方法
– メリット:設備が比較的簡単で低コスト
– デメリット:高温により香りや風味が損なわれやすい - (2) 真空蒸留法
– 真空状態で沸点を下げ、低温でアルコールを蒸発させる方法
– メリット:香りや味を保ちやすい
– デメリット:設備コストが高くなる傾向 - (3) 膜分離法(フィルター法)
– 特殊な膜を使ってアルコール分子だけを分離する方法
– メリット:風味をほぼそのまま維持できる
– デメリット:高度な技術と設備が必要
1-2.製法の流れ(例:アサヒゼロ)
- (1) 通常のビールを醸造(麦芽+酵母で発酵)
- (2) 脱アルコール装置でアルコールを除去
- (3) 香りや味の成分を残しつつ、アルコール度数を0.00%に調整
- (4) 最終製品としてノンアルコールビールが完成
アサヒビールでは「ブリューゼロ製法」と呼ばれる二段階の脱アルコール処理を採用しており、より本物のビールに近い味わいを実現している。
1-3.なぜ脱アルコール製法が注目されているのか?
- (1) 健康志向の高まり
- (2) 運転時や休肝日などのニーズ
- (3) 飲み会などで雰囲気を楽しみたい人向け
- (4) SDGsや「スマートドリンキング」への企業の取り組み
1-4.豆知識
- (1) 日本では「ノンアルコール」はアルコール度数0.00%である必要がある
- (2) 海外では0.5%未満でも「ノンアル」とされることが多い
2. 日本国内の脱アルコール製品の市場動向
日本国内の脱アルコール(ノンアルコール)製品市場は、ここ数年で急成長を遂げており、健康志向やライフスタイルの変化を背景に、今後も拡大が見込まれてい。以下に、最新の市場動向を詳しくまとめる。
2-1.市場規模と成長率
- (1) 2023年のノンアルコール飲料市場は**4,133万ケース**(前年比101%)と、10年前の約1.4倍に成長
- (2) 2024年も引き続き拡大が予測され、4,191万ケースに達する見込み
- (3) 飲み会などで雰囲気を楽しみたい人向け
- (4) 特にノンアルコールビールテイスト飲料が市場の中心で、75%以上のシェアを占めている
2-2.消費者の意識と行動変化
- (1) 飲用頻度の増加
– 月1回以上ノンアル飲料を飲む人の約6割が「1年前より飲用量が増えた」と回答
– 若年層(20〜29歳)を中心に、夕食時・休日の昼間・飲み会など多様なシーンで飲用されている - (2) 飲用理由
– 主な理由は「おいしさ」「種類の増加」「健康」
– 「最近おいしくなったと聞いて」「気分を上げたいとき」「リフレッシュしたいとき」など、感情的価値も重視されている
2-3.製品カテゴリーの広がり
表1. カテゴリーと特徴
| カテゴリー | 特徴 |
|---|---|
| ノンアルコールビール | 味の再現性が高く、機能性表示食品も登場 |
| ノンアルRTD (レモンサワー・チューハイなど) |
若年層に人気。選ぶ楽しみが増加 |
| ノンアルワイン | 「食事を華やかにしたい」「くつろぎたい」など のニーズに対応 |
– 機能性付き製品(内臓脂肪を減らすなど)を選ぶ人も6割以上に増加
– 「正気のサタン」「Ciraffiti」などのクラフト系ノンアルも登場し、個性派需要にも対応
2-4.社会的背景と企業の取り組み
- (1) アルコール離れの進行
– 国税庁のデータによると、成人1人あたりの酒類消費量は1992年のピーク時から約75%減少
– コロナ禍による飲み会の減少、Z世代の「酔わない社交」志向が影響 - (2) 企業の戦略
– アサヒ・キリン・サントリーなどが「スマートドリンキング」や「休肝日」文化を推進
– サントリーは「2030年までにノンアル・低アル製品の構成比20%以上」を目標に掲げる
3. 他の飲料における脱アルコール技術
脱アルコール技術はビールだけでなく、ワイン、日本酒、カクテル、スピリッツ、さらには機能性飲料など、さまざまな飲料に応用されている。それぞれの飲料には独自の風味や成分があるため、技術の選択や工夫も異なる。以下に詳しく解説する。
3-1.飲料別の脱アルコール技術
- (1) ワイン
– 膜分離法(逆浸透膜)や真空蒸留法が主流
– ワインは香り成分が繊細なため、低温・低圧での処理が重要
– 脱アルコール後にアロマ成分を再添加することで、風味を補完 - (2) 日本酒
– 日本酒は米由来の旨味や酵母の香りが特徴
– アルコール除去には減圧蒸留法が用いられ、雑味を抑えつつ旨味を残す工夫がされる
– ノンアル日本酒は、食中酒としての需要が高まっている - (3) ノンアルカクテル(モクテル)
– 元々アルコールを含まないレシピも多いが、既存のカクテルからアルコールを除去する製品も登場
– 香りや口当たりを再現するために、植物由来のエキスや香料を活用。
– 炭酸や酸味を加えることで、飲みごたえを演出 - (4) スピリッツ(ウイスキー・ジンなど)
– 高度な蒸留技術や分子レベルの分離技術が必要
– ノンアルジンなどは、ボタニカル(香草)成分の抽出により、香りを再現
– アルコールの「熱感」を模倣するために、カプサイシンやジンジャー成分を微量添加する例も - (5) 機能性飲料(CBD・プロテイン・ビタミン系)
– 一部の製品では、アルコールを含む抽出液から成分を分離する必要がある
– 例えばCBD飲料では、エタノール抽出後に脱アルコール処理を行い、成分だけを残す
3-2.技術の選択と課題
表2. 脱アルコール技術と特徴
| 技術 | 特徴 | 適用例 |
|---|---|---|
| 真空蒸留法 | 低温で香りを保つ | ワイン、日本酒 |
| 膜分離法 | 分子レベルで選択的に除去 | ビール、ワイン |
| ストリッピング法 | 高流量で効率的 | ビール、スピリッツ |
| 香料再添加 | 風味の補完 | カクテル、スピリッツ |
– 課 題:風味の損失、コスト、設備の複雑さ
– 解決策:香り成分の回収・再添加、植物由来素材の活用
3-3.世界的な動向
- (1) 欧州ではノンアルワインやノンアルジンが高級志向で人気
- (2) 米国では「ソバーキュリアス」層向けにノンアルスピリッツ市場が急成長
- (3) 日本では「休肝日」文化や「スマートドリンキング」が背景にあり、ノンアル日本酒やカクテルが注目されている
3-4.未来の可能性
- (1) AIによる味の最適化や、分子レベルでの香り再構築が進行中
- (2) 発酵制御技術と脱アルコール技術の融合で、より自然な味わいが実現可能に
- (3) 「飲まない」ことが「選ぶ」ことになる時代へ
4. 脱アルコール製法の具体的な利点
脱アルコール製法には、単にアルコールを除去するだけでなく、味・香り・健康・社会的価値など多方面にわたる利点がある。以下に、技術的・消費者的・社会的観点から詳しく解説する。
4-1.技術的な利点
- (1) 本物の味わいを再現できる
– 一度通常のアルコール飲料を醸造し、そこからアルコールを除去するため、発酵由来の複雑な香味成分が保持されやすい
– 特にビールやワインでは、麦芽やブドウの風味、酵母のニュアンスが残るため、“本物に近い”味わいが実現可能 - (2) 香気成分の保持が可能
– 最新の膜分離技術や真空蒸留法では、香り成分を損なわずにアルコールだけを除去できる
– 例えば、アルファ・ラバル社のRevos濃縮システムでは、0.0%製品でも**高級アルコールやエステルの保持率が高いとされている - (3) 製品の安定性と品質向上
– 脱アルコール処理により、微生物の繁殖リスクが低下し、保存性が向上
– 高圧処理や低温処理により、酸化や劣化を防ぎやすい
4-2.消費者にとっての利点
- (1) 健康志向にマッチ
– アルコール摂取を控えたい人(妊娠中、運転前、休肝日など)でも、味や雰囲気を楽しめる
– カロリーや糖質が低い製品も多く、ダイエットや生活習慣病予防にも貢献 - (2) 飲用シーンの拡大
– 昼間の食事、仕事中のリフレッシュ、運動後の水分補給など、従来のアルコールでは難しかった場面でも飲める
– 飲み会での「雰囲気合わせ」や「酔わない社交」にも最適 - (3) 選択肢の多様化
– 微アルコール(0.5%未満)や完全ノンアル(0.00%)など、好みに応じた選択が可能
– 味のバリエーションも豊富で、クラフト系やフルーツ系など嗜好性の高い製品が増加
4-3.社会的・環境的な利点
- (1) 飲酒文化の多様化と包摂性
– アルコールが苦手な人や宗教的に制限がある人も、同じ場で楽しめる
– 「飲まないこと」がネガティブではなく、ポジティブな選択肢として認知されるようになる - (2) 環境負荷の低減
– 濃縮物として輸送することで、輸送回数やCO₂排出量を削減できる
– 製造工程での水やエネルギー使用量の最適化も進んでいる
4-4.代表的な事例:アサヒゼロの「ブリューゼロ製法」
- (1) 通常のビールを醸造 → 2段階の脱アルコール処理 → アルコール度数0.00%を実現
- (2) 味や香りの成分を残しながら、完全にアルコールを除去する高度な技術
- (3) 消費者からは「本物のビールに近い」と高評価
脱アルコール製法は、単なる代替技術ではなく、新しい飲料文化を創る革新技術ともいえる。
5. 今後の市場予測
日本国内のノンアルコール飲料市場は、今後も力強い成長が見込まれている。以下に、2025年以降の市場予測を述べる。
5-1.市場規模の予測
- (1) 2024年:市場規模は約376億米ドルに到達
- (2) 2033年:市場規模は約758億米ドルに倍増すると予測
- (3) 年平均成長率(CAGR):7.70%(2025〜2033年)
この成長率は、飲料業界の中でも非常に高く、特に健康志向やライフスタイルの変化が市場を牽引している。
5-2.成長を支える主な要因
- (1) 健康・ウェルネス志向の高まり
– 低糖質・無添加・機能性飲料(ビタミン強化、プロバイオティクスなど)の需要が急増
– 予防医療や生活習慣病対策として、ノンアル飲料が選ばれる傾向 - (2) 若年層の価値観の変化
– Z世代を中心に「酔わない社交」や「ソバーキュリアス」が定着
– SNSやサブスク型の直販モデルが若者の消費行動にマッチ - (3) プレミアム化と多様化
– クラフト系ノンアル、高級茶・ジュース、RTD(Ready to Drink)コーヒーなどが人気
– 季節限定・地域限定商品が話題性と売上を両立
5-3.製品カテゴリー別の成長予測
表3. 製品カテゴリー別の成長傾向
| カテゴリー | 成長傾向 |
|---|---|
| ノンアルコールビール | 味の再現性向上で安定成長 |
| ノンアルRTD (チューハイ・カクテル) |
若年層に支持され急成長 |
| ノンアルワイン・高級飲料 | 食事とのペアリング需要で拡大 |
| 機能性飲料(ヨーグルト、スムージー) | 健康志向層に支持されて急伸 |
5-4.流通チャネルの変化
- (1) オンライン販売が急成長。Amazonや楽天での定期購入が増加
- (2) サブスクリプションモデルやSNS直販がブランド戦略の鍵になる
- (3) コンビニ・スーパーでも「ノンアル専用棚」が拡充中
5-5.サステナビリティと植物由来飲料
- (1) アーモンドミルク、オーツミルク、豆乳などの植物性飲料が拡大
- (2) 環境配慮型パッケージ(生分解性素材など)も消費者の選択基準になる
5-6.今後の注目ポイント
- (1) 機能性表示食品としての展開(脂肪燃焼、集中力向上など)
- (2) AIによるパーソナライズ提案(好みに応じた飲料レコメンド)
- (3) 海外市場への輸出やインバウンド向け商品開発も加速
この分野は、単なる「代替飲料」から「新しいライフスタイルの象徴」へと進化している。この製法は、単なる「アルコール除去」ではなく、味わいの再構築でもある。まるで、雨上がりの森で香りがふわっと立ち上るように、風味を丁寧に引き出す技術といって良い。
以上