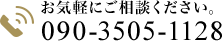2025/10/06
『食品機械・機器(加工・製造装置)の基礎知識』
“Food Machinery and Equipment (Processing and Manufacturing) Basic Knowledge”
【Ⅰ】. はじめに
食品製造工程別にラインを構成する 「食品加工・製造」に関連する代表的な食品機械・機器(装置)について製品別に解説する。
1. 原料タンク
原料タンク(tank)とは、飲料メーカーや食品工場で主に液体原料の保管や混合調合に使用されるタンクで、「サニタリタンク」と呼ばれる。洗浄がしやすく、汚れが残りにくい仕様で、直接原料や製品に触れる接液部は主にステンレス製である。オーステナイト系、フェライト系、マルテンサイト系などのステンレス鋼が使われ、各々が耐食性や加工性、溶接性に優れている。これらのタンクはサイロタンク、ストレージタンク、ジャケット付タンク、エージングタンクなど様々な種類があり、原料貯蔵、調合や保温保冷、発酵、洗浄といった多用途に用いられる。
2. エクストルーダ
エクストルーダとは、粉体状またはペースト状の原料を混錬し、高温の状態で加熱、装置内のスクリューで加圧し、押し出すことによって成型、加工する多機能の食品加工機器である。押し出して成型するというところから(EXTRUDE:押し出して成形する)という名前が用いられている。エクストルーダはもともと、射出成型のプラスチック製品などの工業製品を生産するために開発された装置であるが、原料を押し出して成型する仕組みを食品の加工分野でも活かして現在では様々な食品がこの装置で製造されている。
3. 粉体供給(排出)装置
粉体供給機(フィーダ)とは、粉体を次のプロセスの粉体処理機器に供給する装置。一般的にはゲートの開閉調節や回転速度、振動力等の可変によって供給量が制御される。ホッパースケールや搬送コンベヤ等と組み合わせることで、供給から排出までの工程を自動化できる。
4. 食品用スライサ
スライサとは、肉類や魚類・野菜等、固形状のものをスライス(薄切り)、短冊切り、おろし、ダイスカットなどの形状に加工する装置または器具全般を指す。スライサを使って一定の薄さや細かな形状にすることで、形が揃う、かさが減る、火の通りがよくなる、味がしみ込みやすくなるといった利点がある。食品の種類やカットしたいサイズや形状、処理能力などに応じて、手動のものから電動のものまで幅広い種類のスライサが用いられている。
5. フライヤ
フライヤとは、食品を高温の油の中で加熱する装置。油の対流熱によって熱が伝わり、食品に油の香味を加える材料が高温の油の中で熱せられると、水分が減少し代わりに油を吸収する。 高温のため、材料に適当な焦げ味が付き風味を増すことができる。食品工場でフライヤを用いた製品としてはコロッケ、から揚げ、てんぷらなどの惣菜食品で多く使われている。一方、ノンフライヤとは、熱風を上から下へ高速に対流循環させて食材全体を一気に加熱し、油を使わずに本来食品に含有される水分や油分を利用して歯ごたえのよい揚げ物を作ることができる調理装置である。
6. ふるい装置
ふるい機(篩機)とは、一定の網目を有するふるいに粒体を入れて振動させることで、粒の大きさに応じて粒体を分別する装置。ふるい機を使用することにより、粒径の材料を規定範囲内ごとに選別して複数種類の製品を製造と共に、異物除去ができるため、粒状製品の付加価値や品質の向上に寄与することができる。主に、粒状・粉状・角状原料の分別に使用され、調味料やソースといった液状の分別にも使用されることがある。
7. 混合装置
混合機(ミキサ)とは、2種類以上の原料を、攪拌羽を用いてかき混ぜる、又は原料を投入した容器を回転させるなどして混ぜ合わせる装置。混合機で混合する原料は固体、液体、気体など様々なケースがあり混ぜ合わさるのに最適な混合方法は原料種類によって変わりる。攪拌羽を用いる場合でも、羽の形状と釜の形状、攪拌する速度や時間によって、混合後の原料状態が変わる。
8. 乾燥装置
乾燥機とは、乾燥物の水分を飛ばす装置。乾燥させる食品によっては保存性を高めることができる。主にドライフルーツ・ジャーキ・海産物・香辛料・お茶・ヨーグルト、ペットフード等を製造する際に用いられる。農産物の6次産業化や海産物の干物生産に活用が進んでいる装置である。
9. 加熱装置
加熱装置とは、材料や製品に熱を加える装置。熱のかけ方によって製品の味や色、香り、風味などが左右されるため、品質向上を図るには加える熱の温度や時間の管理が重要になる。また夏場の時期に発生リスクの高い食中毒を引き起こす原因菌の多く(O157、サルモネラ菌、芽胞菌など)は熱処理によって死滅させることができる。食品衛生法で多くの食材・食品に対して加熱処理などによる殺菌・滅菌が義務付けられており、法律上の基準を満たしながら、より美味しい商品を生産するために加熱装置が多くの製造現場で採用されている。
10. 焼成装置
焼成装置とは、加熱蒸気や赤外線を利用して、短時間で食品を焼成する装置。高温の加熱蒸気を利用するタイプを加熱蒸気式、強力な赤外線を利用するタイプを光加熱式と呼ぶ。これらの装置は、コンベヤ上を流れる食品に対して加熱蒸気を噴霧したり、数種類の赤外線を照射したりすることで、焼成の加減を調整する。加熱蒸気式は、食品を焼くと同時に蒸すことができるため、しっとりとした仕上がりが得られる。一方、光加熱式は、水蒸気が適さない食品にも効率よく焼成を行うことができる。焼成装置は、窯としての役割も果たし、食品の焼成に加え、冷凍食品の解凍、様々な食品の焙煎、殺菌にも利用される。また、焼成装置は、食品の成形後の焼成に使用され、食品の内部温度を十分高く保つことで、強度と品質を向上させる。焼成中にはガスの発生があり、電気を利用することで精密な温度管理が可能で、一般的に、焼成過程では素材の強度や風味を増ことができる。
11. オーブン
オーブンとは、食品を蒸し焼きにするための調理器具。熱せられた空気と食品から発生する水蒸気を器内に閉じ込め、100℃以上に加熱して調理を行う。直火焼きのように食品が強い熱で焦げたり、強い収縮で固くなったりすることがなく、口あたりや風味のよい料理を作ることができる。オーブンの一種に、スチーム発生装置によって熱と蒸気をコントロールするスチームコンベクションオーブン(通称スチコン)がある。スチコンは、1台で複数の調理方法を可能とした多機能の加熱調理機器で、蒸し焼き以外にも、炒める・煮る・揚げる・炊く・茹でるなどの調理も可能である。
12. ロースタ
ロースタとは、主に肉や魚などの食材を蒸し焼きや炙り焼きにするための調理器具。オーブンとの違いは、オーブンは対流熱で加熱するのに対し、ロースタは側方や上方から輻射熱で加熱していく。ロースタ一台で「焼く・煮る・蒸す」といった調理工程をすべて行うことが可能なものもある。ロースタ庫内の酸素濃度を0.5%と低く設定することにより、加熱水蒸気の品質を向上させることで食材の酸化を抑制、加熱時間を短くして旨味の流出防止することが可能である。短時間で調理を行うことにより、食材からの水分蒸発を抑えることで水分の流出を防ぐことができ、結果的に食材本来の色や鮮やかさを保持することができる。
13. 成型装置
成型装置とは、原料生地を流し込み、型を用いて一定の形状に加工する装置。ミートボールやコロッケ、ハンバーグやメンチカツ、はんぺんやつくね、チョコレートにキャンディー等様々な食品の成型に用いられます。成型装置には、ハンバーグ成形機やパスタ製造機、包餡機や製パン機など、多種多様な機械があり、製造される物や原料の材質によって使用する機種は異なります。小麦粉を主原料とするものや、魚肉練り製品やミンチ肉を原料とするものなど、原料によって採用する成型装置の仕様も大きく異なる。
14. 均質化装置
均質化装置とは、食品(主に液体)の粒子を細かくして均一化させるための装置。成分や密度、品質などにムラが無い状態にすることで品質が上がり、加工もしやすくなる。牛乳や豆乳の粒子を均一化する際に用いられる。また、チョコレートやマーガリンのように油と水を乳化させる際にも用いられる。均質化をすることがホモジナイズともいわれるため、異なる物質の粒子を細かくして均質にするための機械はホモジナイザーという。
15. コーティングマシン
コーティングマシンとは、製品の周りにコーティング物を塗布するための装置。主に、チョコレート、ガム、豆類、飴、グミといった製品の周りにコーティング物を塗布する装置のことを指す。コーティングの用途のみではなく、製品の整形や艶出し、複数味製品のアソート(3味混合)品の混合を行うために用いて様々な用途で採用されている。他にも液状またはクリーム状の原料(センター)を対象物に塗布する装置として使用されたり、チョコレートや砂糖、ソース、醤油、タレ等の塗布といったり、汎用性の高い装置である。
16. 串挿し装置
串挿機とは、焼き鳥などのように食材に串を挿す事に特化した専用装置である。焼き鳥の串に肉を刺す串打ちという作業は、機械化、自動化することは難課題といわれていましたが、串に刺した肉を焼くときに肉が回らないように串打ちをする必要があり、職人の技術が必要で機械では再現ができなかったためである。今現在では1時間に6000本を串に刺すことができる装置も開発され上市されている。これまで手作業で行っていた串打ちは50~60本が限度とされてたが、大幅なスピードアップを実現しただけでなく、固さの違う部位の肉を正確に串挿ししたり、冷凍食材にも対応した串挿し機も開発されている。
17. フィッシュカッタ
フィッシュカッタとは、名前の通り魚類の頭部をカットする、3枚おろしにする工程を自動で行う装置で、魚のみではなく、イカ、カニ、エビ、昆布などの魚介類も含めてカット装置の総称。魚類は多くの場合、頭部、尻尾、内臓、ウロコ、皮など可食部とそれ以外に分ける必要がある。カニの加工機の中でもズワイガニ、タラバガニそれぞれに合わせた仕様の加工機が必要になるため、加工する製品のサイズや重量、特性を整理した状態で仕様を検討していくことが重要である。魚の種類も同様に加工するサイズに合わせて装置設計をする場合が多いため、使用目的を明確にして装置を選定することが大切である。
18. 自動皮剥き装置
自働剥き機とは、主に根菜(イモ類、ニンジン、大根など)や果物(リンゴ、パイナップルなど)、魚類などの皮を自動で取り除く装置。省スペースで使用できる小型のものから、特に根菜類においては大量処理が可能な連続式まで、ラインナップがある。これまでの自動剥き機では、食材の食感を損ね、ピーラーの刃で食材の可食部を大きく削ってしまうなどの問題を抱えていたが、その問題を解決するために、現在はピーラーの刃を排除した仕様の自動剥き機も開発されている。改良された自動剥き機では可食部を削りすぎずに皮を剝くことができるようになったことで歩留率の向上にもなっている。歩留率の向上は廃棄物の量も大幅に減少させるなど環境負荷の低減に貢献している。
19. 洗浄装置
洗浄装置とは、シャワーやバブリングなどの水流を利用して、食品や製品から異物を除去するための洗浄機である。この装置は、虫や毛髪、動物毛、貝殻片、食材のヌメリなどを効果的に除去し、品温を下げて後工程での加工を容易にする機能を持っている。さらに、原料の残留農薬を基準値以下にするためにも活用され、食品の品質保護を実現する。葉物野菜、根菜類、果物、食肉、水産物など、様々な食材に対応可能で、連続した洗浄が可能である。
20. 脱水装置
脱水機とは、原体洗浄を行った原料やカットした後に殺菌、冷却を行った原料の水分を飛ばすことに用いられる装置。原料に含まれる余分な水分を飛ばすことによって、後工程での混合や最終製品になった際の食感や見栄えなどをよくするために脱水を行う。主にはレタス、白菜、ほうれん草、人参、大根、キャベツ、ネギ等の水切りに使用し、洗濯機の脱水機能と同じ原理を用いて、原料をカゴに投入している状態でカゴを高速回転させることによって生まれる遠心力を用いて脱水をする。原料の水分をコントロールすることは食品製造において大変重要な要素であるため、脱水機は食品工場だけでなく幅広い食品製造現場で採用されている。
21. トレー供給装置
トレー供給機とは、プラスチックトレーや発泡トレーなど食品を盛り付けるためのトレーを1枚ずつ供給する装置。スーパーマーケットなどの小売販売形態で水産加工物、畜産生鮮食品、加工食品など、食品トレーは数多くの場面で使用されている。盛付け工程においては、トレーが1枚1枚自動的に流れてくることでライン化が可能になり、生産効率を向上させることができる。トレー供給を自動化することによって省人化できるだけでなく、人手作業が介在しないことでトレーの供給姿勢が安定し、毛髪等異物混入対策にも繋がるといった効果がある。
22. 搬送・振分装置
搬送・振分装置とは、前工程から流れてくる製品を後工程の設備能力に合わせて分配、供給するための装置。包装機への投入部分の滞留具合を検出しながら複数台の包装機へ分配供給したり、製品の搬送姿勢を正して整列させたりと前後工程のバランサ的機能も持つ。搬送する製品の特性やサイズ、スピードに合わせて搬送方法、振分方法も変えることができる。同じ製品を搬送する場合でも装置メーカーやエンジニアリングによって装置の活用方法も多種多様の工程が構築できるといった特徴を持っている。
23. 冷蔵・冷凍装置
冷凍装置とはフロンやアンモニアといった冷媒ガスを使用して、蒸発→圧縮→凝縮→膨張というサイクルを回す事により、熱を移動させ、製品温度を氷点下まで下げることが可能な装置。食品を製造する工程の一つに冷蔵や冷凍を行う工程があり、用途としてはチョコレートを掛けた製品の品温を下げチョコレートを固める、冷凍食品で調理済みの製品を冷凍状態にするといった使い方をされている。食品の流通では、3温度帯といわれる「常温、冷蔵、冷凍」があり、製造現場内での保管、出荷、流通から店舗への陳列まで冷凍装置は不可欠な装置である。
24. 炊飯装置(一連:システム)
炊飯装置とは、炊飯を行うために必要な機能をそれぞれ担う、一連の装置(システム)を指し。炊飯ラインの一般的な工程は「出米」→「洗米」→「浸漬」→「水切り」→「計量、注水」→(調味液、具材添加)→「炊飯、蒸らし」→「取り出し」→「攪拌、ほぐし」→「計量、盛付け」の工程でシステム化されている。スーパーマーケットのプロセスセンターや大規模な給食センター(セントラルキッチン)などで自動炊飯ラインが導入されている場合が多く、比較的小さな炊飯ラインでは「炊飯・蒸らし」工程のみ自動化を行うなど自工程の処理能力やレイアウトに合わせて自動化を進められている。
25. 殺菌装置
殺菌装置とは、食品そのものや機器、工場内などの対象物に付着、発生する細菌や微生物に対して作用する装置。主な作用としては、抑制、除去、殺菌・滅菌・消毒などがあり、機器によって作用が異なる。菌の発生・増殖には以下の4つの条件①温度、②栄養、③水分、④酸素量が関係する。食品の殺菌は,加熱処理や洗浄・薬剤処理によって行われることが多いが、一部の微生物の生残や洗剤・薬剤の残存が懸念される。その中でも加熱水蒸気による殺菌装置は洗剤・薬剤の残存がなく安全で、熱による食材・食品の品質の劣化を最小限に留めながら,微生物に対して確実な殺菌が求められる。
26. パン粉付装置
パン粉付装置とは、食品にパン粉を付ける工程で使用される装置。別名で粉付機やブレッダ、衣付機などの呼び方もされる。大量生産向きのものや少量多品種向きのものがあり、冷凍食品や総菜、コンビニなどの弁当を製造しているラインでフライヤの前工程として主に使用される装置である。衣付作業を手作業で行う場合、作業を担当する人によって衣をつける量がバラツクなどの問題が発生するが、自動化することで省人化だけでなく生産の安定化、商品の品質にも寄与する装置である。
27. ろ過、分級、濃縮装置
ろ過装置とは、ろ過材を搭載したろ過をするための装置。一般に業務用でろ過装置というときは、液体のろ過を目的とするものを指す。食品製造においては、主に飲料や、チョコレートやクリーム、清酒や醤油等の製造工程の中で使用される。製造工程の中では固形物と液体を分けて次工程で使用する製品の抽出や、ろ過器を通過させることによって製品を滑らかにしていく工程で使用されていることが多い。
28. 麺類製造装置
麺類製造装置とは、麺類を製造する際に使用される一連の装置のことを指す。麺類の一般的な製造工程として「原料の溶解」→「原料混合、ミキシング」→「複合、熟成」→「圧延、ローリング」→「切り出し」→「茹で」→「水洗、冷却」→「包装」といった流れで製造されている。スーパーマーケット惣菜、コンビニ惣菜、カップラーメン、冷凍食品などで販売されている麺類の製造で使用されている装置である。
29. 解凍装置
冷凍食品を解凍する方法を大きく分けると、急速解凍と緩慢解凍がある。急速解凍とは、熱を加えて迅速に解凍させる方法。緩慢解凍とは、常温解凍、低温解凍、流水解凍など時間をかけて解凍する方法である。急速解凍と緩慢解凍のどちらが優れているということでなく、食品の種類や用途によって、適切な解凍方法があることから食材に合わせて解凍方法及び装置を選択する。食品工場では原料が冷凍された状態で納品されることも多く、解凍装置を使うことにより、原料からのドリップ(原料の液汁)の流出を抑制することができ製品の物性にも影響する。
30. 熟成・発酵関連装置
発酵関連装置とは酵母・細菌などのもつ酵素によって、糖類のような有機化合物が分解して、アルコール・有機酸・炭酸ガスなどを生ずる現象を製造するための機器。醤油や味噌、酒などを製造するための一連の装置を指す。発行を伴う製品の一般的な製造工程として「原料処理」→「製麹」→「仕込」→「圧搾」→「製成」→「充填・包装」という流れで製造される。
31. 製パン装置(一連:システム)
製パン装置とはパンを製造するために必要となる一連(システム)の装置を指す。パンを製造するためには一般的に「混合、ミキシング」→「一次発酵」→「生地分割」→「ベンチタイム」→「成型」→「二次発酵」→「焼成」→「包装」という流れで製造されます。製菓製パンを製造する機械装置として構成する一連の装置は、①オーブン、➁ミキサ、③ホイロ ④モルダ、➄急速凍結機、⑥冷蔵庫、⑦冷凍庫である。
32. 製粉製造装置
製粉製造装置とは一般に小麦,穀類などを破砕して,その皮を取除き,内質にあたる部分を粉にするための装置。製粉製造の工程として一般的には「精選」→「調質」→「配合」→「破砕(ブレーキ)」→「ふるい分け」→「純化工程」→「粉砕(スムースロール)」→「ふるい分け」→「採り分け」の流れで製造される。工場の生産工程に用いられるものには,ロール型製粉機 (ロールの間で粒をつぶすもの) や衝撃型製粉機 (突起のある回転板を高速度で回転させて粒に衝撃を与えるもの) ,ひき臼型製粉機などの装置がある。
33. 破砕・粉砕装置
対象物を大まかに砕くものを破砕といい、より小さく砕くのを粉砕という。どのくらいの大きさにするかによって機種(装置)が変わる。使用用途に合った種類を選ぶ必要があり、製造工程では原料の一次加工や混合工程で主に使用される。
34. 圧搾装置
圧搾装置とは食材の実、種子、茎などから、液分、油分をしぼり抽出する装置。絞り機や搾汁機も圧搾装置の一種である。食材の減容の用途で粉砕装置や圧搾装置を使用することもあり、加工品の原料として使用するエキスやピューレのように絞った側を活用する場合と、和菓子などの中身として使用する餡のように絞る装置側に残ったものを活用する場合がある。
35. 自動開袋・開梱装置
自動開袋装置(粉体原料袋用)は紙袋やビニール袋から粉粒体などの内容物を取り出す際に異物混入や装置内への粉粒体の飛散を防ぎ、衛生を保つ装置が追加された開袋装置になる。粉体原料は紙袋に封入されている場合がほとんどで、段ボールの開梱装置との仕様が大きく異なる。段ボールと紙袋の開梱方法だけでなく、開梱精度や開梱に伴う異物に対する対策も重要な要素になる。
36. 熱交換装置
固体、液体、気体を問わず、熱は高温から低温へ移る性質がある。この性質を利用して、効率的に熱を移動させる装置のことを「熱交換器」という。食品工場において、熱交換器はチューブ状や板状の金属、樹脂などを介して、液体や気体を熱したり、冷やしたりすることで、さまざまな用途に使われている。 簡単な原理として例えば、一本の金属管に加熱した温水を通すと管の回りの空気は温められ、温度は上昇する。逆に管の中の温水は空気によって冷やされ、温度は下降する。また、用途に応じて,冷却器,凝縮器,復水器,加熱器,予熱器,蒸発器などと呼ばれることがある。
37. スライサ
スライサとは主に、食材別に食材を均一で薄切りにするための装置。異なる食材や食品カテゴリーは異なる衛生基準に従う必要がある。専用のスライサを使用することで、異なる食材を処理する際に衛生基準を維持しやすくなり衛生基準が確保することができる。また、専用のスライサは特定の食材や製品に最適化することで生産性が向上し、特定のスライサは特定の用途に特化しており、それによって効率的な生産ラインを構築できる。これらの専用あるいは特定のスライサは、自動化されたプロセスで食品の生産性を向上させ、均一性を確保するために設計されている。
39. 撹拌装置・ミキサ
撹拌装置・ミキサとは主に、食品加工や製造現場で使用され、材料を混ぜ合わせ均一な物質の表面や内部の構造、感触、質感や組成を作るための装置。攪拌機は液体や粉体などの異なる成分を混ぜ合わせ、均一な混合物を作る際に最適な装置である。ミキサは異なる種類の原料や製品に対応できる柔軟性があり、混合物に合った撹拌羽根を使用することで、様々な処理が可能である。
40. 蒸気・スチーマ加熱装置
蒸気・スチーマ加熱装置とは主に、食品加工や製造現場で使用される。蒸気加熱装の事を「スチーマ」または「蒸気ジェネレータ」といわれる。これは蒸気を生成して食品の調理、加熱、処理に利用される装置である。食材を蒸すための装置で、通常は蒸気を生成して食品を加熱する。
41. 製菓製パン・米飯 成型装置
製菓製パン成型装置とは主に、生地を特定の形状に整形するための装置。これにより、パンや菓子などの製品が均一で所定の形状にする。成型装置は、生地をこねたり伸ばしたりして、最終的な形状に整えるプロセスを担う装置である。また、クッキー、クレープ、バームクーヘン、ベーグル等の特殊な形の成型に特化した装置もあります。米飯成型装置は、餅の搗上げ、ライスケーキ、おにぎり、寿司等の製造ラインに導入されている。
42. 冷蔵庫・冷凍庫
冷蔵庫・冷凍庫とは主に、大規模なプロセスで使用され、大量の食材や製品を効率的に冷却・保存する。通常、厳格な衛生基準や業界の規制に従って設計され、専門の冷却技術を備えている。その厳格な衛生基準の例には、定期的な清掃と消毒・温度管理・衛生的な取り扱い・食材の保管。これらの基準は、食品の品質と安全性を確保し、衛生リスクを最小限に抑えるために設けられている。
43. 超音波カッタ
超音波カッタとは、超音波振動により刃物を振動させ対象物を切断する機械です。食品加工の現場においては、通常の刃物では切断しにくいものを切断する際に広く用いられます。また、ハンディタイプの小型の物から、コンベヤや画像認識を組み合わせた大型の全自動の物(例えば、ホールケーキなどのカットなど)まで、様々なラインナップがある。
【Ⅱ】. 最後に
次回は『食品機械・機器(充填・包装装置)の基礎知識』として食品製造工程別にラインを構成する代表的な食品機械・機器(装置)について製品別に解説する。
以上
【参考文献】
「食品設備・機器事典」編集:食品設備・機器事典編集委員会 発行:産業調査会