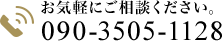2025/09/25
再エネの切り札が正念場を迎えている。三菱商事を中心とするグループが、千葉県銚子市沖と秋田県由利本荘市沖や能代市沖の3海域の大規模洋上風力発電事業から撤退。洋上風力拡大を急ぐ日本政府、そして事業に協力する地元に衝撃が走った。
日本政府が30年間海域を利用できるよう法律を整備し、これまでに10の海域で事業者が決まっているが、3海域はその先駆けの事業で、三菱商事が中部電力の子会社などと2021年に落札。あわせて134基の風車で、2028年以降170万kWの発電を始める計画だった。世界的なインフレや円安で資材や人件費が高騰し、建設費が当初の想定の2倍以上に膨らんで事業費が1兆円を超えて採算が見込めなくなったとして、撤退を発表した。
日本は風車製造から撤退したため輸入せざるを得ず、この事業では羽根はイギリス、発電機部分はデンマーク、支柱は中国製で為替の影響を受ける。さらに設置には大型の専用船が必要。現場海域で船の底から脚を4本伸ばして船体を海底に固定し波の影響を受けないようにして部材を設置する必要があり、事業費がかさむことになる。さらに建設費が膨らむことになった。
三菱商事の事業は契約の時期の違いや、出力が1.3倍と大型の風車が使われる計画だったため、資材の高騰の影響を強く受けることになったといえる。そもそも契約の当時、三菱商事のグループは、他社より2割以上安い売電価格を提示して3海域を総取りした。海外のノウハウや風車の大型化を見越しての低価格だったとみられるが、その見積もりに甘さがあったのは否めない。
今年決めたエネルギー基本計画で、全電源の1%あまりにとどまる風力を、2040年度に最大8%に拡大する方針を打ち出している。陸上風車は景観や騒音問題で計画中止も相次いでいるため、問題が起こり難いとされる洋上風力で多くをまかなう方針で、2040年に3,000万~4,500万kW、大型火力およそ20基分の発電能力の事業を決める目標としている。
脱炭素と電力の安定供給へ再エネの拡大は不可欠で、洋上風力が頓挫してしまってはならない事情もある。3海域が洋上風力に適していることに変わりはないことから、撤退の影響を抑える対策を急ぐ必要がある。
日本は四方を海に囲まれており、再エネの中でも洋上風力の潜在的可能性は大きいものがある。この地の利を生かすと共に現在抱えている洋上風力発電について、日本政府は課題の洗い出しと対策を早急に打ち出してほしいものである。
以上